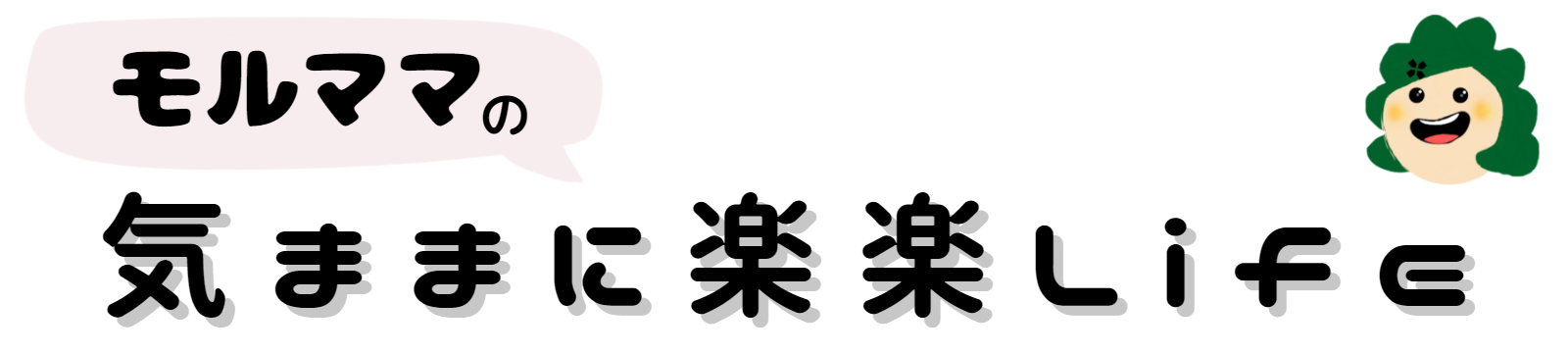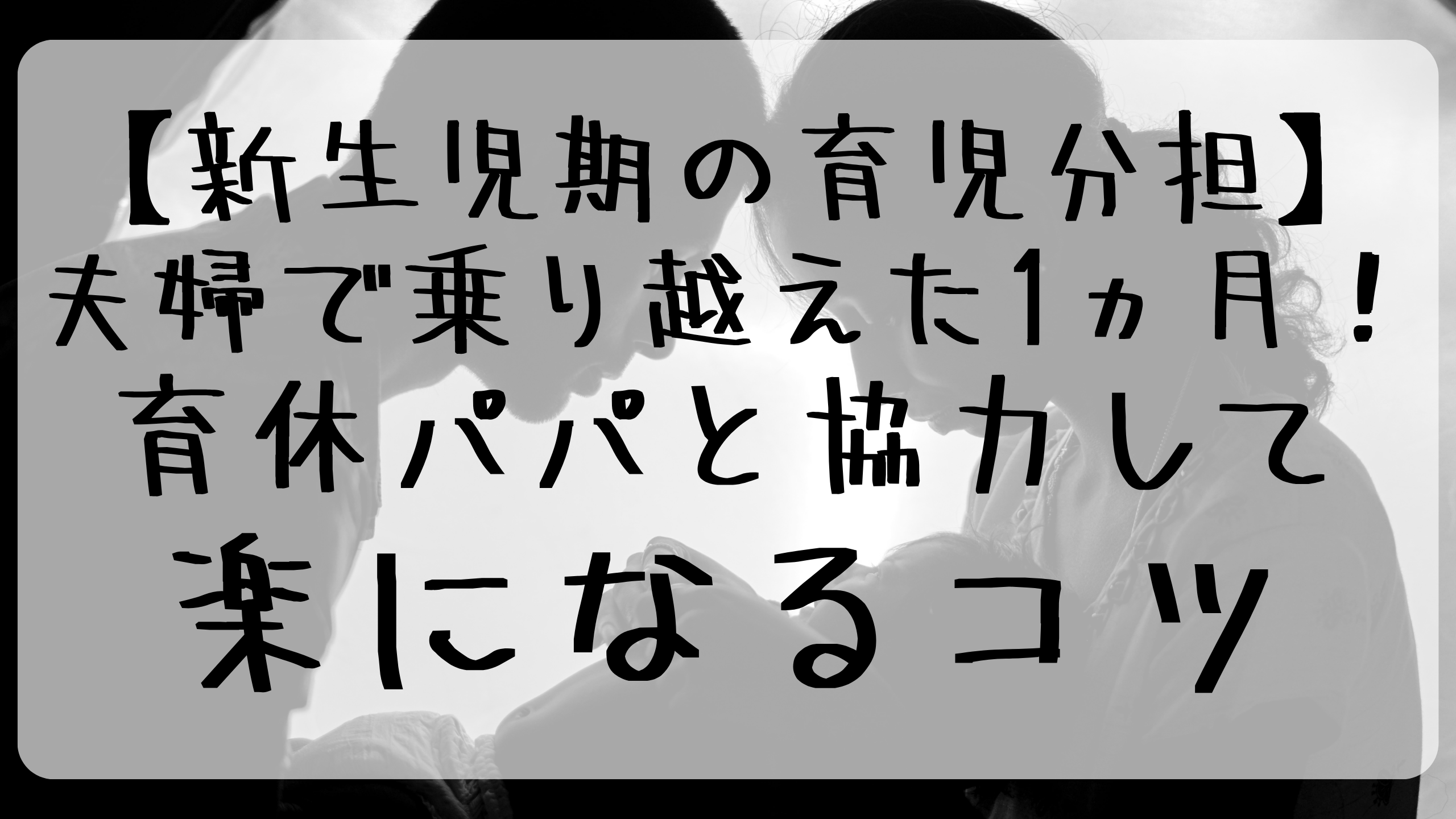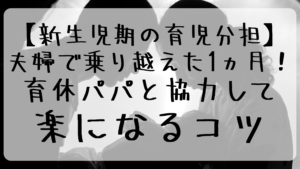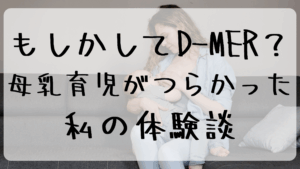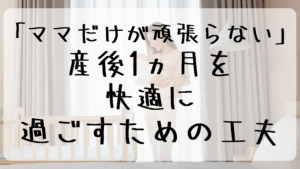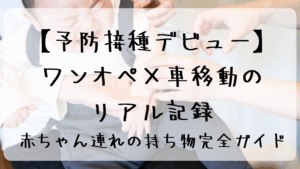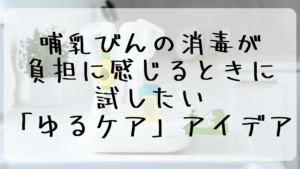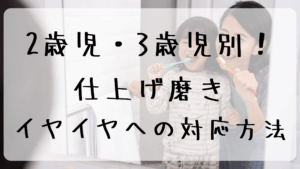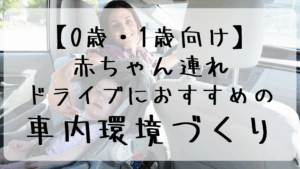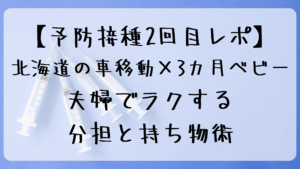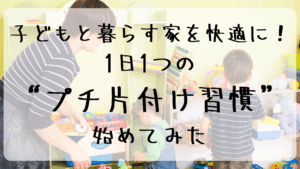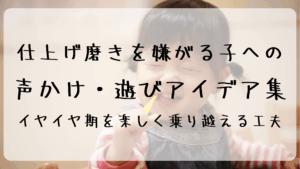こんにちは、モルママです。
我が家では、里帰り出産はせず、自宅で夫婦二人三脚で新生児育児に挑みました。
夫は育休を1ヵ月取得してくれたのですが、これが思った以上に心強く、今では「本当にあの1ヵ月があってよかった」と感じています。
でも、最初からすべてがうまくいったわけではなく、手探りの毎日。
夫婦で「誰が何をやるのか」決めるまでにも少し時間がかかりました。
今回は、実際にやってよかった育児・家事の分担方法と、うまく回すコツを体験談とともにまとめました。
もくじ
我が家のリアルな分担パターン
我が家では家事はママが中心、赤ちゃんのお世話は授乳以外パパが中心というスタイルに落ち着きました。
◆ママの担当
- 軽めの食事作り(基本は簡単なもの)
- 洗濯や片づけ(体調と相談しながら)
- 母乳での授乳
◆パパの担当
- オムツ替え・着替え・沐浴
- ミルク全般(調乳・授乳・消毒・洗浄)
- 役所手続き・買い物などの外出系
- 夜間の寝かしつけサポート(ママの休息時間確保)
母乳とミルクが半々だったため、ママが授乳に縛られすぎず、体力的にも精神的にもすごく助かりました。
家事をママが担当してよかった理由
正直、私ひとりで家事も育児も…なんて絶対無理。でも、育児の大部分を夫に頼れたので、家事は無理のない範囲で自分のペースでこなせました。
というのも、うちの夫は元々家事にあまり慣れていなかったんです。もし丸投げしていたら「洗い方が雑」「そのやり方は違う」と私がイライラしてしまって、険悪な空気になっていたと思います。
その点、自分で家事の基準を決めてやれるのはラクでしたし、ロボット掃除機や食洗機、冷凍食品、宅食サービスにも頼って、産後の自分を追い込まないようにしていました。
夫が育児に関わるメリット
新生児期の1ヵ月を夫がフルコミットで育児に関わってくれたおかげで、その後も自然に赤ちゃんのお世話に参加してくれるパパになりました。
はじめはおっかなびっくりだった沐浴も、3日目には「俺の仕事」って感じでスムーズに。
おむつ替えも授乳後のげっぷも、すっかり私より上手です。笑
この“パパを育てる”期間があるだけで、ママの負担がぐっと軽くなるんだと実感しました。
とはいえ夜のお世話も任せていると不安も出てくるもの。
ベビーモニターを設置していたおかげで、朝に「こんなことがあったよ」と共有しあえてよかったです。
分担をうまく回すコツ
- 完璧を目指さないこと:適当でいい、というおおらかさが大切
- 言葉で「お願い」「ありがとう」「助かった」を伝える
- お互いの限界を尊重する:「今日は眠い」「休ませて」もOK!
- 報連相をこまめに:アプリ「ぴよログ」が神ツールでした
ぴよログでは、授乳・ミルク・おむつ・ねんねなどを記録してシェアできるので、「今ミルクあげた」「次おむつ頼むね」といった連携がスムーズでした。
夜間のミルクやおむつ交換も記録に残っていると、「夜中も大変だったんだな」と自然にねぎらう気持ちになりました。
我が家はぴよログとアレクサを連携したので、声で記録できるようになり最強に便利に。
接続方法だけ面倒なので後日接続の方法も共有したいなと思ってます。
入力忘れてもベビーモニターで映っていればさかのぼって時間を確認できるのも助かりました。
まとめ:ママ1人で抱えこまないで大丈夫
出産を控えているママにとって、「ちゃんと育児できるかな…」という不安はつきものだと思います。
でも大丈夫。完璧じゃなくても、夫婦で協力すればちゃんと乗り越えられます。
大切なのは、ママが産後の回復に集中することと、パパが育児に関わる経験を積むこと。
どちらも「助け合い」と「思いやり」があれば、きっとうまくいきます。
この1ヵ月の経験が、今の私たちにとってかけがえのない財産になりました。
同じように迷ったり不安を感じているママにとって、この記事が少しでも参考になればうれしいです。