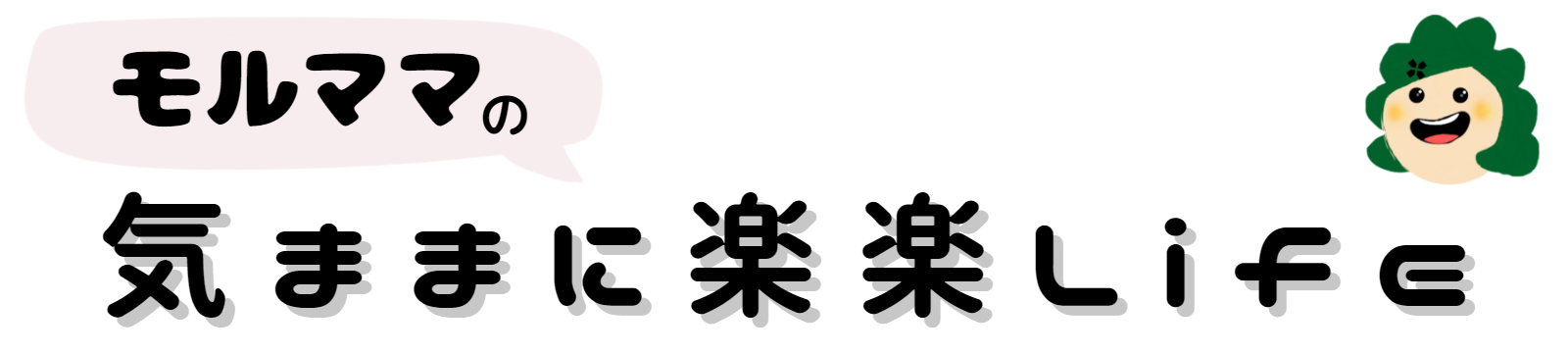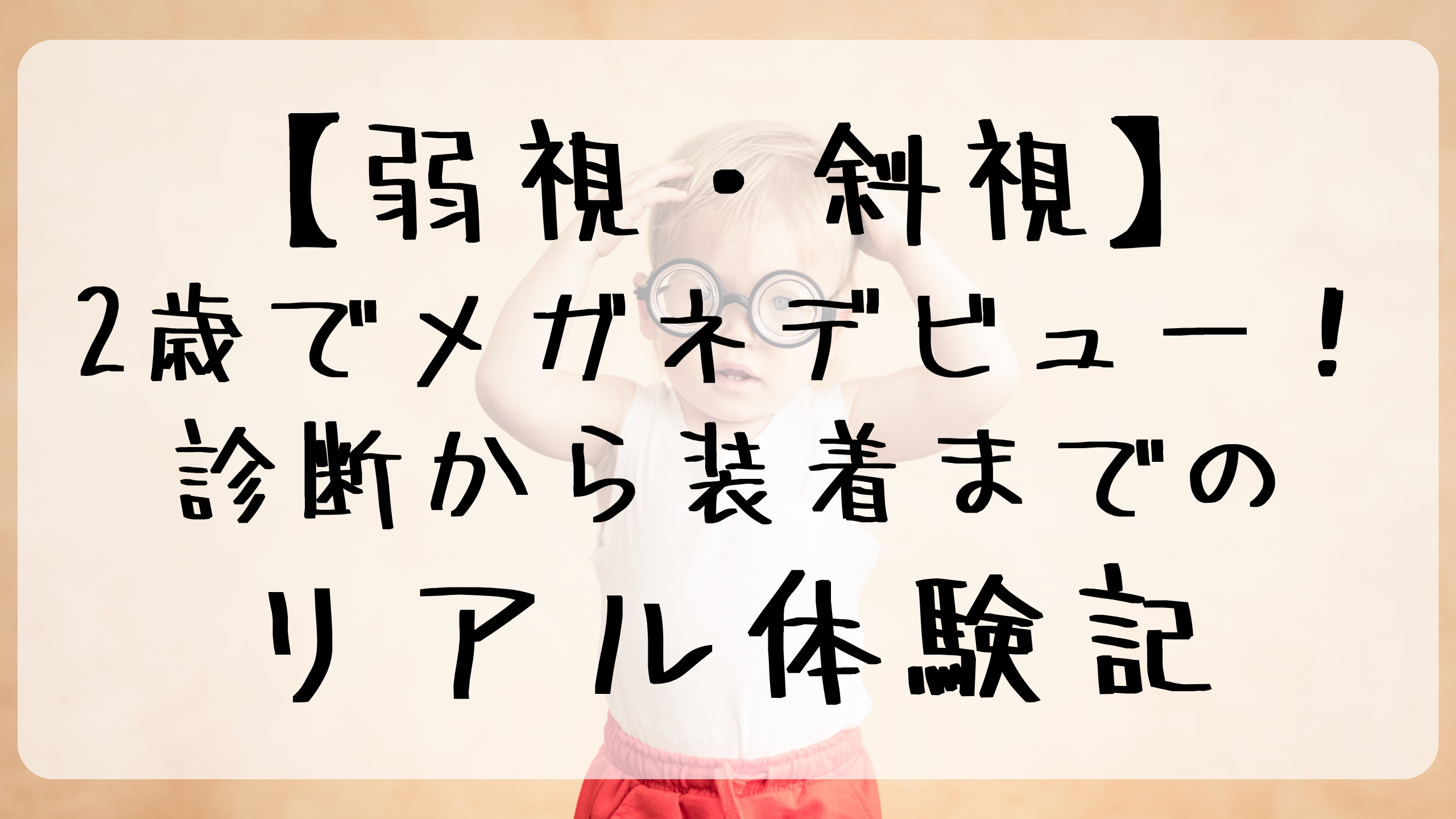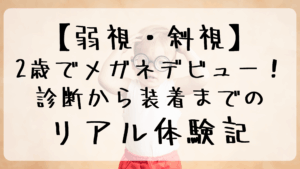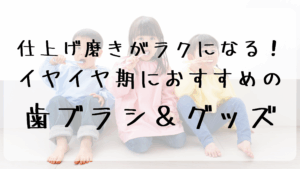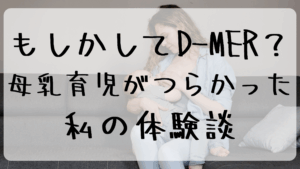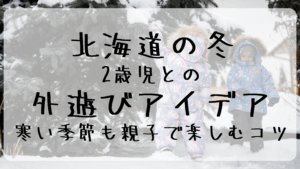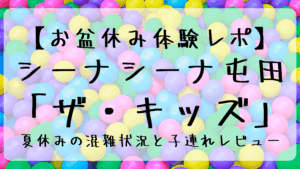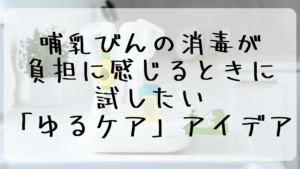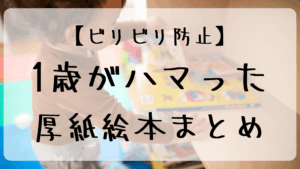娘が2歳のとき、小児眼科で右目の遠視性乱視と間歇性斜視、そして弱視と診断されました。
これまで何となく視線が合わないな、転びやすいな、と思っていたものの、「まさか見えていなかったなんて…」と驚いたのが正直な気持ちです。
今回はそんな我が家の初受診からメガネ生活スタートまでの経緯を、詳しく振り返ってみたいと思います。
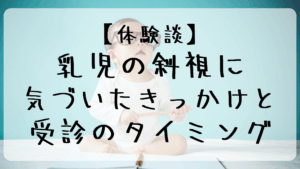
初めての眼科受診|2歳1か月
どこの病院へ行けばいいかも分からず、普通の眼科では「3歳以上でないと難しい」と断られることもありました。
保育園の看護師さんに相談して、ようやく2歳1か月で小児眼科を受診できることになりました。
初回は以下のような検査を行いました。
- 屈折検査(オートレフラクトメータ)
- 絵視標検査(ランドルト環ではない)
- 眼位検査
- 立体視検査(偏光グラス着用)
- 調節麻痺薬の点眼 → 再度屈折検査
初めての場所にもかかわらず、娘は遊びだと思ったのか落ち着いて検査を受けられました。
医師の診察では、右目が間歇性斜視と遠視性乱視で、視力は右0.3、左0.8とのこと。
斜視の見た目に気を取られていましたが、まさか「見えていない」ほどとは…。
今思えば、よく転ぶ子だったのも視力の影響だったのかもしれません。
この日は検査のみで、次回1か月後に再検査という流れになりました。
2回目の受診|2歳2か月
2回目の検査も前回と同様の流れで行いました。唯一、調節麻痺薬の点眼はしませんでした。
今回は待ち時間にもそわそわして落ち着きがなく、検査中も気を引くのに一苦労。それでもなんとか最後まで検査できました。
初めて検査用メガネを10分ほど装着してみました。最初は嫌がったけれど、「似合ってるね」と声をかけると嬉しそうにかけてくれました。
その後の診察では「弱視」と診断され、メガネ装用が決定。
覚悟していたものの、ぐっと心が重くなるのを感じました。
診断書・処方箋・助成金関係の書類を受け取り、即日眼鏡市場へ。
子ども用メガネの種類は少なかったですが、最小サイズを選んで発注しました。
完成まで10日かかるとのことだったので、その日のうちに眼科の予約を取りました。

正直、最小サイズってめったに出ることがないらしく、種類が少なすぎて…
次、作り変えるときには遠くても、こどもメガネ専門店へ行こうと思います。
3回目の受診|2歳3か月
メガネ完成後、再び眼科へ。
検査は毎回同じ流れ。今回は最も落ち着きがなく、年相応の活発さが目立っていました。
おもちゃやシールブック、お気に入りのぬいぐるみで何とか気を引くも、とても大変でした。
診察ではまず「メガネが落ちている」と指摘され、メガネ用バンドの使用をすすめられました。
あとで待ち時間に楽天で4種類ほど購入。結局、最安の1本が使いやすくて今も継続中です。
斜視に関しては手術が必要とのことで、3か月半後の予約を取りました。全身麻酔の予定ですが、日帰り手術とのことでした。
詳しい説明は手術の一か月前にあるそうで、今回は予約とって説明書類を受け取るのみでした。
また、遠視性乱視による弱視のためのトレーニングとして、アイパッチを導入することに。
視能訓練士さんの説明によると、片目ずつ30分間の手作業(お絵かき、粘土、シール遊びなど)をする必要があるとのこと。
朝の時間にまとめて取り組むスタイルでスタートし、追加のアイパッチは楽天で購入しました。



病院で一か月分のアイパッチを購入しましたが、高すぎた!
楽天のほうが2/3の金額で買えたので、直近分だけ病院で購入すればよかったです…
アイパッチトレーニングは現在進行中
正直、アイパッチは親にとっても子にとってもハードル高めです。
それでも「少しでも楽しい時間にしよう」と心がけて、一週間なんとか乗り切りました。
これからも少しずつ慣れて、習慣にしていけたらと思っています。
アイパッチを毎日続ける工夫についてもまた後日お伝えしたいと思います。
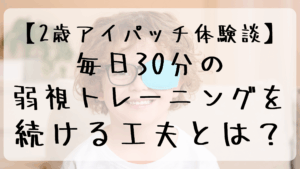
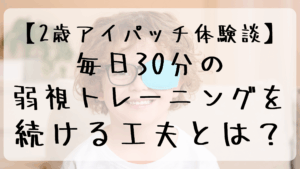
まとめ:早期の気づきと受診が未来を変える
もし少しでも「視線が気になる」と感じることがあれば、迷わず相談してみてください。
2歳というタイミングでも、ちゃんと診断・治療は進められます。
我が家は保育園のスクリーニング検査と看護師さんの助けがあって、ようやくここまで来られました。
正直、市の検診だけだったら三歳児検診まで様子を見ていたかもしれません。
小児弱視は早期発見早期治療が大切だと言われています。
早く気づけば回復が期待できる視力障害ですが、子どもは「見えにくい」と言えません。
弱視も斜視も、早期に見つけて対処することで、将来の見え方を守ることができます。
この記録が、どこかで誰かの気づきや勇気につながることを願っています。